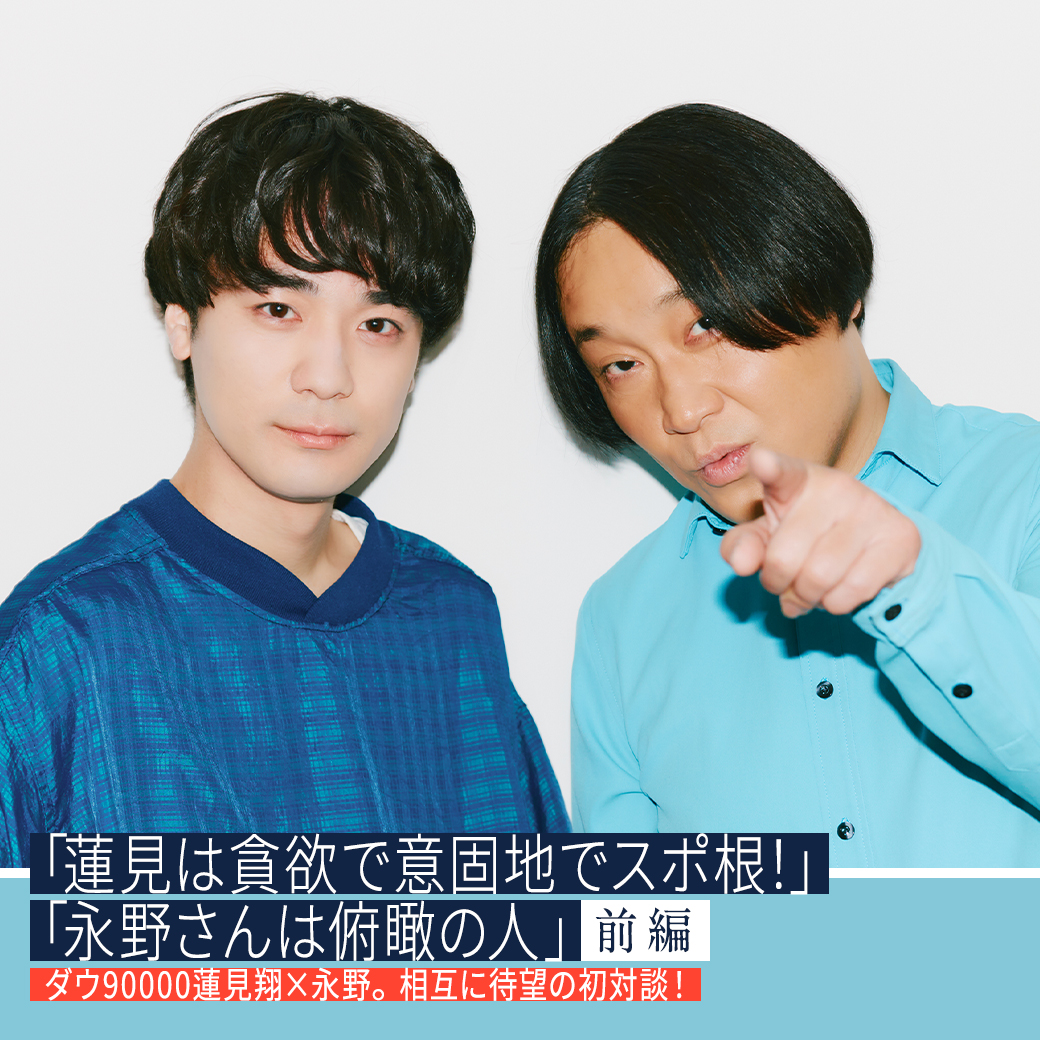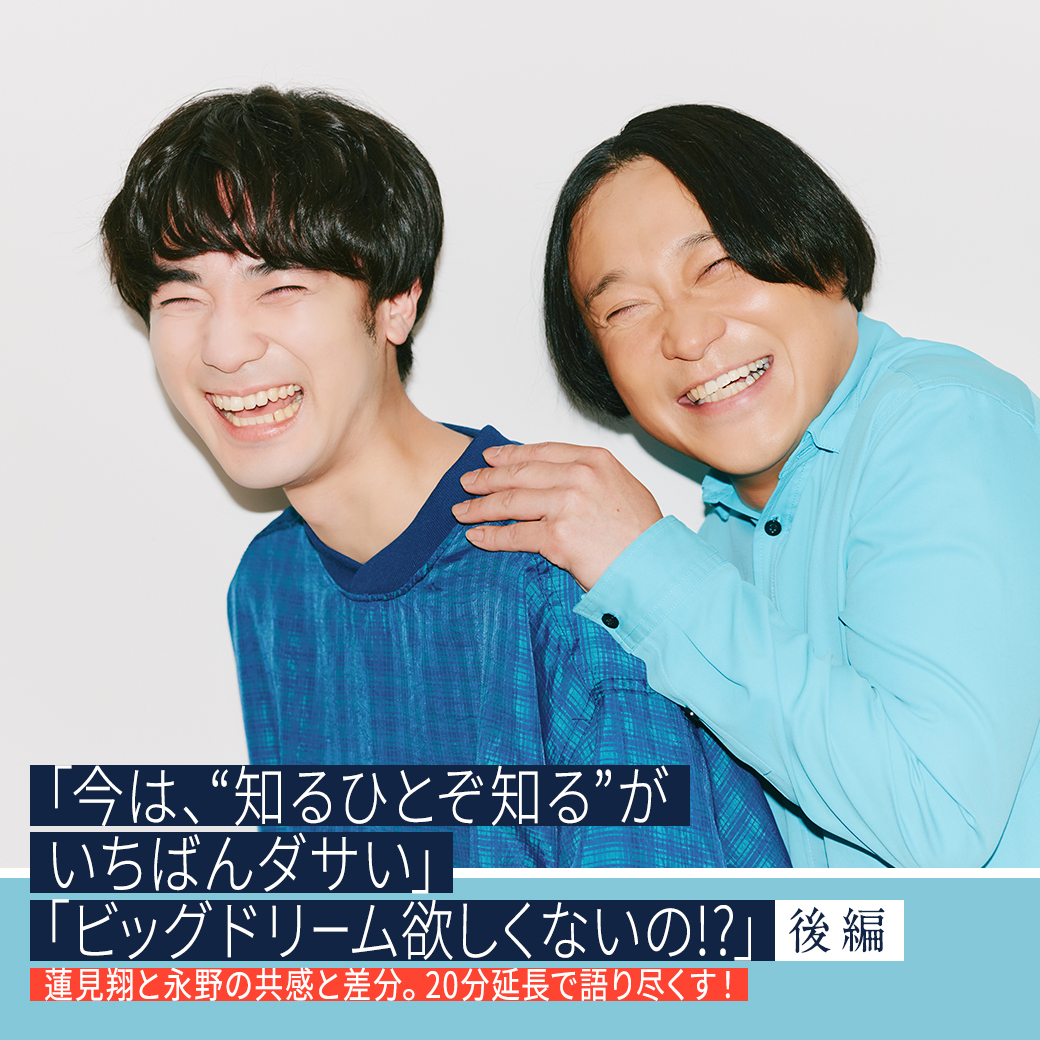過剰なものをつくりながらも、過剰さを求めすぎない
——「タンスの角をLV100にするアイテム」を拝見したのですが、「やりすぎ」なユーモアに笑わずにはいられませんでした。藤原さんは創作に取り組むにあたって「過剰さ」を意識されていますか?
藤原 「無駄づくり」には、たしかに「過剰」な要素があるように思います。けれど一方で、ものをつくる際は「過剰さ」に一線を引くよう意識しているんです。
——そうなんですか! 発明品から受ける印象と真逆のスタンスにおどろきます。
藤原 「無駄」ときくと、アレもコレもといろんな機能がついていたり、複数のマシンが合体していたりと複雑なイメージを抱くと思うのですが、わたしがつくる「無駄」は、だいたいひとつの機能にしぼられています。Youtubeの動画編集では情報を詰めこみすぎないよう、余白を意識していますね。
——あえて余白をつくるのは、視聴者にわかりやすく伝えるためでしょうか?
藤原 わかりやすく、というよりはわたしの美意識の問題だと思います。
たとえば、わたしは「床の間」が好きです。一畳にも満たないちいさなスペースに花器と掛け軸だけがある。そのシンプルで簡素な空間に魅力を感じます。もし床の間にいろんな種類の花をケバケバしく飾ったら、それは美しいとはいえないですよね。
だから「無駄づくり」も、余計な情報を入れず、けずるところはけずる。余白をつくって見る人に感想をゆだねる。過剰なものをつくりながらも、過剰さを求めすぎないように気を付けています。

——「無駄づくり」のインパクトは「やりすぎる」のではなく、むしろ「やりすぎない」ことで表現されているのですね。余白への意識は、創作をはじめた当初からあったのでしょうか?
藤原 いえ、最初は技術がなかったので見よう見まねでつくっていたのですが、そのうちに、余白があったほうがおもしろいと感じるようになりました。
というのも、デヴィッド・リンチの映画『イレイザーヘッド』のなかに、すごく好きなシーンがあって。主人公の男性がエレベーターに乗り込んで行き先階のボタンを押すんだけど、扉がなかなか閉まらなくてしーんとする場面です。妙な沈黙が流れる「間」がおもしろい。その「間」を自分で表現したいと思って創作をつづけています。
——ものづくりをするうちに、自分の好きなものや表現したいことがわかってきた。
藤原 そうです。自分の「好き」や「やってみたい」が漠然としているひとは意外に多いと思います。わたしもそのひとりでした。けれど、手を動かしつづけると自分の輪郭が鮮明になってくるんです。
それを知ったのは「無駄づくり」を本業とする前、お笑い芸人をしていたときです。ネタを書きはじめた当初は誰かのマネのようなものばかりでした。けれど回数を重ねるうちに自分自身の表現ができるようになってきて。
創作を通じて自己表現する。これは自分を知って、受け入れる行為でもあるんですよね。

——創作で自分を受け入れる……? どういうことでしょうか?
藤原 創作に打ち込むと、ネガティブな経験や感情も前向きにおもしろがれるようになるんです。たとえば、バーベキューに誘われなくて悲しい、会社をサボりたい、そんな後ろ向きな感情もアイデアの種にすると「自分はこんな人間なんだ」と開き直れます。
——「強制笑顔マシーン」を思い出しました。無表情に見られるコンプレックスを逆手にとった藤原さんにしか生み出せない名作です。
藤原 自分のありとあらゆる面を受け入れて、創作に昇華する。その作業が作家性を生むのだと思います。ものづくりをつづけるうちに、コンプレックスに起因する生きづらさは次第になくなっていきました。

思いついたら手を動かす
——「無駄づくり」という新しいジャンルをつくり、その活動を10年以上つづけてこられたキャリアにも「過剰さ」を感じます。そもそも「無駄」をコンセプトにものづくりをはじめたきっかけはなんだったのでしょう?
藤原 お笑い芸人として活動していたときに、YouTubeのコンテンツづくりにチャレンジしたのがきっかけです。ピタゴラ装置のようなものをつくろうとしたら失敗してしまって。
失敗を「無駄」のワードで包み込めば、失敗が成功になるのでは? と思いついて「無駄づくり」をはじめました。
——長年つづけてこられた理由はなんだと思いますか?
藤原 他にやることがなかったからですね。
——ええ!? 消去法で前例のない道を歩みつづけられるものでしょうか?
藤原 やめたいと思う瞬間はいっぱいありました。会社を休業しようか、就職しようかと検討したこともあります。けれどそういうときに限って、おもしろい仕事が舞い込んでくるんですよね。縁やタイミングの巡り合わせでいままでつづけてこられています。
もうひとつ理由を挙げるとするなら、「思いついたら実行する」を大事にしてきたからでしょうか。とにかく手を動かしつづけているうちに10年が経った感覚です。

——実行を重んじるから、膨大な量の作品を生み出せている……。
藤原 そうだと思います。わたしは不安障害を患っていて、なにかをしていないと不安感や焦燥感におそわれる症状があるんです。なのでなおさら創作への衝動が強いのかもしれません。
つねに頭のなかではなにかを考えていて、「つくらないと」とモヤモヤしています。だからアイデアを思いついたらすぐに実行。手を動かしてものづくりに没頭できていれば心が落ち着きます。
——実行したものの、うまくいかなくて手を止めてしまうことはないのでしょうか?
藤原 思いどおりにいかない状態をたのしみながら、手は動かしつづけますね。なぜなら創作は寛容であるべきだと思うからです。
たとえ失敗してイメージからかけ離れた作品になったとしても、それはそれでいい。つくる過程にたのしいというプリミティブ(根源的)な感情が湧いていたら、それだけで価値がある。そう思って創作に取り組んでいます。

小学生のレベルでずっと生きていきたい
——藤原さんは文芸雑誌『文學界』にて『余計なことで忙しい』を連載し、最近出版されたリレーエッセイ『私の身体を生きる』にも寄稿されています。執筆活動でも、まずは手を動かすことを重視されているのでしょうか?
藤原 そうですね。基本は頭のなかに浮かんだ順番で書いていきます。
わたしは文章でかっこつけることがあんまりなくて。どちらかというと、自分のかっこわるさをさらけ出すのが文章だと思っています。なので普段使わないようなむずかしい言葉は書きません。かっこいい言い回しも使いませんね。
——思えば、数々の発明品や動画も全然かっこつけていません。10万人を超えるYouTubeの登録者やおおぜいの読者の目があるなかで、かっこつけずにいられるのはすごいと思います。
藤原 数字はあまり気にしたことがありません。もちろん見てくれるひとが多いのはうれしいのですが、ひとの目を気にしすぎると自分の軸がブレるというか、フォームが崩れてしまうような気がして。
一方で、視聴者や読者を悲しませたり、不快にさせたりする要素は極力排除したいとも思っています。ご年配の方には理解できないかなとか、子どもが見たらショックを受けるかもしれないなどは考えますね。「他人の目」をどこまで気にかけるのか、そのバランスがむずかしいです。
「他人の目」を想像しつつも、自分がおもしろいと思うものを小学生のレベルで創作していくのが理想かなと思います。

——小学生ですか……! たしかに大人は「有益性」や「効率性」を求めてしまいがちですが、子どもはただただ手を動かす過程そのものをたのしんでいますよね。藤原さんの創作ポリシーに共通します。
藤原 創作だけでなく、日々の暮らしのなかにも、自分は小学生のようだと感じる場面がよくあります。
以前、夫から言われた何気ない一言が原因で号泣してしまうことがありました。ついつい夫と自分を比較して、自分のダメさ加減に気が滅入ってしまったんです。
その日の夜、こんな些細な出来事で泣くなんて子どもみたいだと思いながらお風呂を済ませてパジャマを着ると、どうも着心地がわるい。なにかおかしいと思っていたら、なんと第二ボタンの下から頭を出していたんです。
——かわいすぎるハプニングです(笑)。
藤原 自分の姿にお腹をかかえて笑っちゃいました。泣いたり、笑ったり、喜怒哀楽の感情の揺れ方が単純で、やっぱりわたしって小学生のまま生きているのかもしれない。
かっこわるくていいし、小学生のレベルのままでいい。手を動かす過程や日々の暮らしをたのしみながら、自分らしく生きていきたいですね。

*****
普段からクリアフレームメガネを愛用されている藤原さん。この日、JINSのメガネを手に取りながら「軽くてかけやすいし、フレームの透明感がキレイでいいですね」とおっしゃってくださいました。
「思いついたら実行する」「過程をたのしむ」「継続する」。
このシンプルで力強い信条が、道をひらき、個性をかがやかせるのだと藤原さんの生き方から教えてもらいました。
JINSも「アイウエアのこれから」をもっともっと考えて、トライ&エラーを繰りかえし、ブランドの魅力をみがいていきたい。そう改めて思った取材でした。